多分岐高分子「ハイパーブランチポリマー」その技術の概要と用途
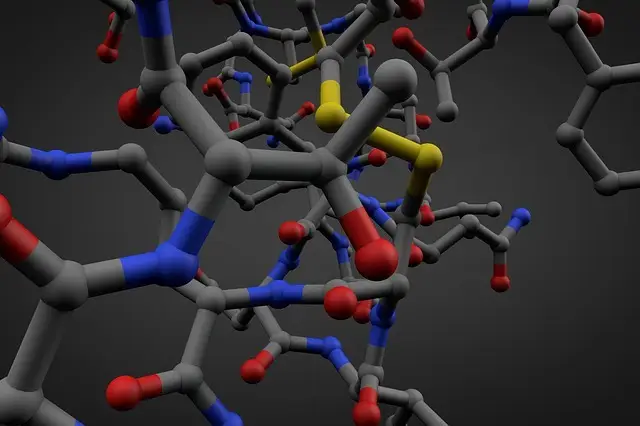
直鎖状高分子と比べて分子中に多数の分岐を持つハイパーブランチポリマーは、非晶質、高い溶解度、溶液中で低粘度であるといった特徴を有する。本稿では、ハイパーブランチポリマーとは何か、また、どのような分野に応用されるのかについて解説する。
ハイパーブランチポリマーとは?デンドリマーとの違い
Diaminobenzoic Acid はリン酸系縮合剤を用いると溶液中で連続的に縮合し、分岐高分子が得られる。こちらの論文にあるFig.1の図のようになる。同様に、2種類以上の官能基(下図の例の場合はアミノ基とカルボキシル基)を持つモノマーから一段階重合で得られる多分岐高分子をハイパーブランチポリマーと呼ぶ。
多くの分岐を持つ高分子として近年ではデンドリマーが注目されるが、両者の大きな違いは重合反応の精密さだ。
デンドリマーは完全な(枝の長さが全て同じ)分岐を作るために多段階の重合反応が用いられるのに対し、ハイパーブランチポリマーは一段階の重合を行っているだけなので各枝の長さも分子自体のサイズもランダムになる。
簡易な反応で完結するためコスト効率の面ではハイパーブランチポリマーが優位だ。
デンドリマーは薬剤送達や化学センサーなどの高級な用途を志向することが多いが、ハイパーブランチポリマーは価格の低さを活かし、塗料やフィルム材料として用いられることが多い。用途については後述する。
直鎖高分子と比較したハイパーブランチポリマーの特徴
従来、高分子合成の分野では直鎖高分子の合成がほとんどだった。これに対し、ハイパーブランチポリマーは以下のような特徴が挙げられる。
高い溶解性と低い粘度
主鎖の構成要素が同じような直鎖状高分子と比較すると、ハイパーブランチポリマーは高い溶解性を示し、溶液の粘度をそれほど上げない。この特徴はハイパーブランチポリマーの分子形状に由来する。
1次元的な構造の直鎖高分子と比べ、ハイパーブランチポリマーは3次元的に空間を占有するため、周囲との相互作用に寄与する実効的な表面積が直鎖高分子より小さい。このため、固体状態における分子間の結合を断ち切って、溶媒分子と新たな結合を形成することが容易となる。
粘度に関しても同様に、ハイパーブランチポリマーは表面積が比較的小さいため、分子間の相互作用が希薄であり、溶媒の自由な移動を阻害しにくい。
溶解度が高いということは溶解に必要な時間を短縮できるということ、粘度が低いということは溶液を吐出させるために必要な力学的エネルギーが小さいということであり、どちらも材料の利便性を高め、工業的な利用の際、有利となる。
末端官能基が多い
直鎖高分子の場合、末端は基本的に2つだ。分子サイズが巨大になれば直鎖高分子全体の特性に末端基が及ぼす影響も小さくなる。
対して、ハイパーブランチポリマーは多くの末端を持ち、末端基が分子の特性に大きく寄与する。末端官能基の種類を変えることで特異な性質を持たせることが可能だ。この特性がハイパーブランチポリマーの応用可能性を広げている。
また、デンドリマーなどでは末端官能基を合成最終段階まで維持するために、これを保護したり、合成手順を工夫したりする必要がある。末端官能基を多く持つ高分子を簡易な合成プロセスで作成できることは、直鎖高分子にも、デンドリマーにもない明確な利点だ。
非晶質
分子が規則正しく配列したものが結晶だが、ハイパーブランチポリマーは形状も分子のサイズもランダムであるため、固体状態で規則的に配列しづらく、非晶性を示すことが多い。
結晶性、非晶性それぞれに利点と欠点があるが、非晶性樹脂の利点としては透明であること、塗装時に基板との接着性に優れることなどが挙げられる。また、熱膨張による体積変化が小さいため、熱溶融を伴う成型で寸法精度を維持しやすい。
製法による形状の変化
ハイパーブランチポリマーの製法は主に2種類ある。
1つは先に述べたように、同一分子内に異なる重合性官能基を有するモノマー(AB_2)を用いて重合する方法(AB2法)だ。この方法はモノマーさえ準備できれば、一段階の重合反応でハイパーブランチポリマーを製造できる。
ただし、このような2種類以上の官能基を持つモノマーはほとんどが市販されていないため、重合反応よりもモノマーの作製に時間とコストを費やすことが多い。
そこで、より少ない労力でハイパーブランチポリマーを作成するために、二官能性モノマー(A2)と三官能性モノマー(B3)を用いる重合方法(A2+B3法)が開発された。
AB2法ではA末端が分子全体に対して非常に少ないが、A2+B3法では分子内に多数のA末端が存在し得る。また、A2+B3法では意図しない副生成物や置換基が生じやすく、一般に反応条件の制御がより難しい。
応用
以下ではハイパーブランチポリマーの工業的応用例を紹介する。
UV硬化樹脂
ハイパーブランチポリマーの応用先として代表的なものにUV硬化樹脂が挙げられる。UV硬化樹脂とは、紫外線照射による連続的な重合反応で硬化する高分子のことを指し、印刷用インク、住宅材料、電子材料などさまざまな用途に用いられる。
ハイパーブランチポリマーを用いることで、UV硬化樹脂の熱的特性や機械特性の改善、生分解性の付与、光反応効率の向上などが報告された。
一例として、大阪有機化学工業ではハイパーブランチポリマーを用いることでUV硬化時の収縮を抑えることに成功している。
従来のアクリル系UV硬化樹脂は、UV硬化に伴う収縮で表面平滑性の維持が難しい。硬化収縮の理由はさまざまだが、硬化前の官能基間の距離と硬化後の結合距離のギャップに由来すると考えられる。大阪有機化学工業が従来生産していたアクリル系UV硬化樹脂では、硬化前の官能基間の距離が3~6Å、硬化後の共有結合距離が1.4Åだった。
同社ではハイパーブランチポリマーを用いることで硬化前の官能基をより密に配置し、硬化による収縮を抑制している。
表面改質
日産化学が開発するハイパーブランチポリマー HYPERTECHシリーズは、塗布膜を形成することで表面の平滑化や剥離性の付与が可能となる。
また、トリアジンを導入したHYPERTECH-URでは、高透明、低HAZE(濁度)かつ平坦性が高いことが特徴で、有機ディスプレイやフレキシブルパネルなどにコーティング剤として用いた際にも高い光取り出し効率を維持できる。
成分保持体
洗剤、石鹸、歯磨き粉などの日用化成品を販売するライオンでは、有効成分の保持体としてハイパーブランチポリマーの活用が検討されている。
ライオンが開発しているのは親水・疎水性や分岐の数を合成条件によってある程度自由にコントロールできるハイパーブランチポリマーだ。親水・疎水性や分岐数を適切に制御すれば、有効成分を内部に保持するだけでなく、有効成分の放散速度を制御することも可能となる。
本技術は香料、殺菌剤、抗菌剤、抗炎症剤、清涼剤、制汗剤、健康食品、着色顔料等、さまざまな用途へ応用が期待される。
まとめ
ハイパーブランチポリマーは日産化学工業のプロダクトのように、すでに実用化されているものがある。一方で、化学、材料工学の分野において、今後、さらなる進化を遂げる可能性もある。
また、東京工業大学大学院ではハイパーブランチポリマーの合成を参考に、デンドリマーの合成プロセスを簡単に進める方法が研究されており、技術の枠を超えた研究開発で新たな展開を見せることもあるだろう。
参考文献:
※1:結晶性樹脂と非晶性樹脂, キーエンス『樹脂成形エキスパート』(リンク)
※2:ハイパーブランチポリアミドの合成と特徴, 寺境光俊(リンク)
※3:【総説】UV 硬化性ハイパーブランチポリマーの合成と応用, 工藤宏人, 「ネットワークポリマー」Vol.37(リンク)
※4:デンドリマー構造を持つアクリルオリゴマー, 猿渡欣幸(リンク)
※5:HYPERTECH®有機ナノ粒子, 日産化学工業(リンク)
※6:機能性材料事業 開発品, 日産化学工業(リンク)
※7:水溶性ハイパーブランチポリマー及び有効成分保持体, Google Patents(リンク)
※8:明るい未来へ分岐する高分子材料, 東京工業大学生活協同組合『LANDFALL』2013年冬(リンク)
【世界の先端材料・新材料の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界の先端材料・新材料の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら









