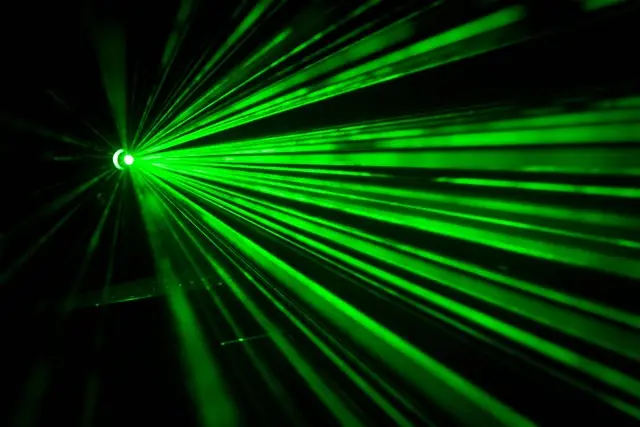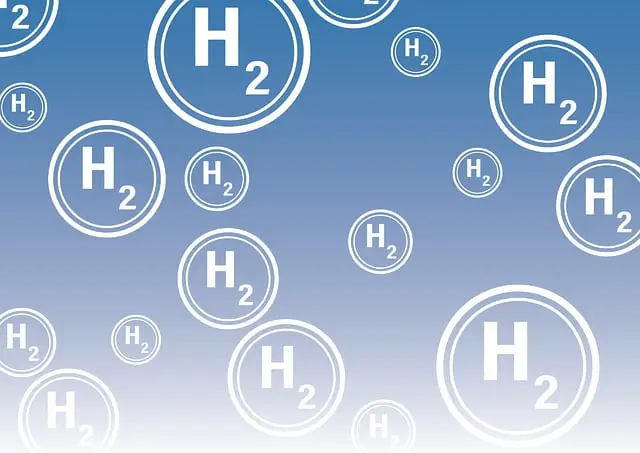DSPチップ開発の米RetymがシリーズDで113億円を調達。これまでの調達総額が270億円超となりステルス状態離脱へ
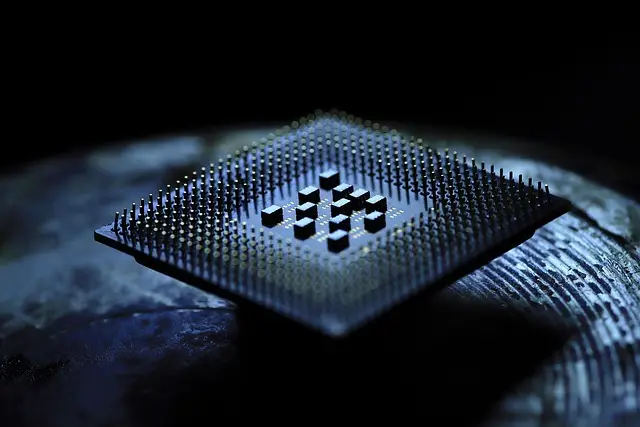
コヒーレントデジタル信号プロセッサ(DSP)と呼ばれる種類のチップを開発する米Retymは2025年3月31日、シリーズD資金調達ラウンドでの$75m(約113億円)の確保を発表した。
Retymは同時に資金調達総額が$180m(272億円)以上となったとしつつ、ステルス状態(存在を秘匿したまま起業)からの離脱を宣言。設立は、2021年だった。
データに対する巨大な需要に「高速化」で応えるチップ
近年のAIブームにより、GPUは需要過多の状態が続き、またデータセンターの建設も相次いでいる。GPU、データセンター関連への投資も非常に盛んとなっているが、一方でチップ以外の何らかの部分で、高速でのデータのやり取りや処理を可能にする設計も、必然的に求められる。
Retymが開発するチップは、こうしたニーズを背景にデータセンター内外のデータのやり取りを高速化するものだ。光の振幅と位相の変調を各拠点でデジタル処理する「コヒーレント光学」というアプローチによるチップとなる。よって、GPUを開発するNvidiaと競合するわけではない。
ステルス状態離脱に際してRoni (Aharon) El-Bahar共同創業者兼CTOが発信したステートメントによると、設立当初はAIに対する意識がそれほどなかったと振り返る。一方で、データセンター間の相互接続が始まりつつ急成長も遂げていたとし、DSPへの強いニーズが生まれているとの確信はあったという。しかし、当時のDSPサプライヤーはイノベーティブに感じず、オープンで協力的なエコシステム構築の必要性を感じ、起業という選択に至った。
こうした経緯から、AIデータセンターへの需要対応以外でも用途が考えられそうだ。
そして、同じステートメントでは、以下のコミットメントを強調している。
イノベーション、オープン性、比類のない専門知識を組み合わせることで、次世代の光インフラストラクチャを強化します。
Retymは、Sachin Gandhi CEOとEl-Bahar CTOによって設立。Gandhi氏はCiscoなどで役職付きの経験を持つ。一方、El-Bahar氏はSamsung、Intel、Huaweiでエンジニアチームの管理職を経験し、Retym設立前にはHuawei Israel Research CenterのCTOだった人物だ。
「画期的なプロダクトの発表が控えている」とCEO
シリーズDには、複数のVC、投資会社が参加した。資金の使途についてRetymは、「AI駆動型ネットワーク帯域幅の高まりに対応するため設計する複数世代の製品ロードマップを描く当社にとって大きな前進」と述べるにとどめ、明確な言及を避けた。
CEOのGandhi氏は、「画期的なプロダクトの発表が控えているが、これは始まりに過ぎない」と、近日中の新たな動きを示唆した。
【世界の半導体の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界の半導体の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら