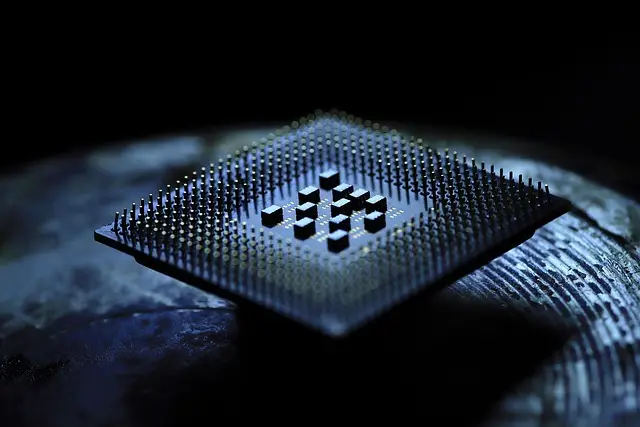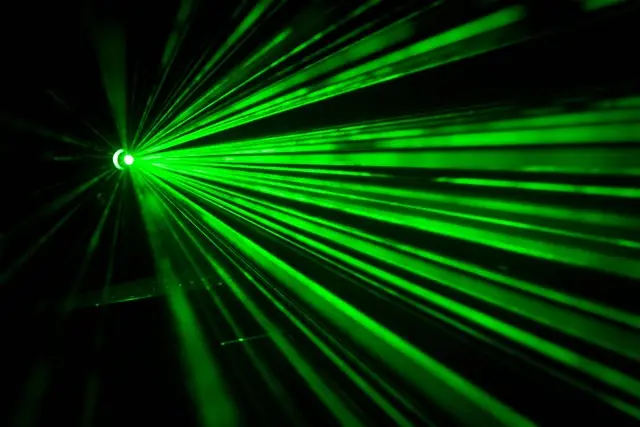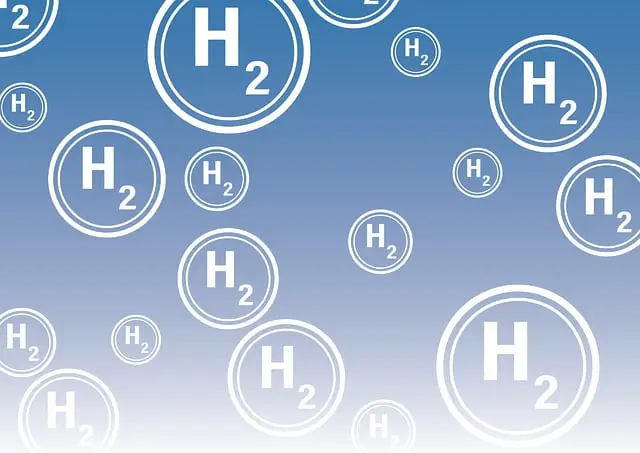夢を解析・制御する技術の研究開発事例、期待されるデジタルヘルスへの応用

人が寝ているときに見る夢は、夢占いなど文化的な切り口から観察するケースが見られる。一方、何らかのトラウマにより悪夢を頻繁に見るといった、精神科的症状を有する人もおり、こうした場合は恒常的なストレスにつながってしまう。
もちろん、投薬やデバイスによる治療などで、それが改善できるに越したことはない。また、治療以前の問題として夢がどう発生するのか、夢を見るときにどのような脳の動きがあるのかといった解明も必要とされる。
そこで、世の中では夢の解析や夢の制御を行うような技術が研究開発されている。本稿では、アカデミズムと企業動向の両面から、夢に関連する技術について取り上げる。
夢のメカニズムの仮説「AIMモデル」など基礎的な研究の現況
人はなぜ夢を見るのか。心理学からのアプローチもあるが、ここでは北海道大学大学院理学研究院の常松友美講師によるレビュー「What are the neural mechanisms and physiological functions of dreams?」を基に、生物学、神経科学の分野からはどのように考えられているのかを見てみたい。
夢の研究で比較的歴史のある学説であり、なおかつ、現在も一定の支持を得ているものに「活性化合成モデル」がある。精神科医のAllan HobsonとRobert McCarleyが1977年に提唱した。この説では睡眠中、脳の外側膝状体と視覚皮質が活性化された上で知覚的情報、概念的情報、感情的情報が合成され、夢になると説明した。さらにHobsonらは、情報の生成には橋膝状体後頭葉(PGO)波が関与しているのではないかと言及している。
その後、ネコ、ラット、サル、ヒト、マウスがそれぞれレム睡眠中にPGO波を発していることが相次いで観測された。
Hobsonは2000年、ハーバード大学医学部のRobert Stickgold教授、マサチューセッツ総合病院のEdward Franz Pace-Schott准教授とともに、活性化合成モデルを拡張させた「AIMモデル」を発表。AIMモデルは仮想の三次元空間内でレム睡眠中の意識状態がどの位置にあるかを示すものだ。三次元空間は、活性化(A、アクティベーション)、インプット(I)、変調(M、モデュレーション)の3つの座標軸(正確には、パラメーター)からなる。より深堀りすると、Aはシステムの情報処理能力、Iは情報の外部入力、Mはシステム内の情報がどう処理されるかを示すものだ。
常松氏はレビューの中で、AIMモデルを基にしたとき、実際にどう夢や脳の動きが起きるかが今後の研究のポイントになる、と記している。AIMモデルも前述の通り一定の支持はあるものの、あくまでも仮説であり、神経科学の面からは夢を見るメカニズムはまだ研究の途上にあるといえよう。
アカデミズムにおける夢研究|夢のモニタリング編・ATRの「解読」
近年のアカデミズムの動きを見てみたい。夢のモニタリング、夢への介入といった2分野の研究を取り上げる。
夢のモニタリングについては、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)によるものだ。国内の大手通信などが出資する民間研究機関、ATRの脳情報研究所・神経情報学研究室は、fMRIで睡眠中の脳活動を計測し、被験者に夢の内容をヒアリングした。具体的には、「本」や「車」など20の物体が夢に登場したか否かを聞くというヒアリングだ。
これを繰り返し、物体と脳活動がどう関連するかのアルゴリズムを構築。次いで、再び睡眠中の脳活動をfMRIで計測すると、夢に現れる物体が相応の精度で解読できるようになった。
ATRはこの結果を、ブレインマシンインターフェースなどでの応用が期待できるとしている。
アカデミズムにおける夢研究|夢に入り込む技術編
夢への介入は、米国の大学での事例、2つを取り上げる。
MITメディアラボ|TDI(夢を導く)研究
米マサチューセッツ工科大学(MIT)内の研究機関であるMITメディアラボでは、Targeted Dream Incubation(TDI)と呼ばれる研究を実施。日本語にすれば、目標を絞った夢の孵化、となる。さらに分かりやすい言葉にすれば、夢を特定のテーマに導く研究だ。
研究では、Dormioと名付けられたデバイスを被験者に装着する。Dormioは、被験者の睡眠状態の追跡(センサーとしての役割)、刺激(主に目標へ向けたキーワードを音声で再生)、夢レポートの記録ができる。
 Dormioを装着した女性(MITメディアラボのプレスキットより)
Dormioを装着した女性(MITメディアラボのプレスキットより)
被験者が入眠すると、Dormioのタイマーが起動。一定時間が経過すると音声で被験者は覚醒状態に戻され、入眠時に見た夢のレポートを声で記録する。それを基に、Dormioから特定の単語を考えるよう音声で促され再度、睡眠。これらの記録や刺激のプロセスが繰り返され、特定の夢が見られるよう近づけていく研究だ。
MITメディアラボはTDIの目的として、以下の3つを挙げる。
個人的内省を促すという哲学的取り組み
夢が人の認知にどう影響するかの探求
精神医療における治療の可能性拡大
3点目については、米退役軍人局とTDIを応用した研究が進められる。心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに悩む元将兵の治療への活用を目指すものと見られる。
ノースウエスタン大学|レム睡眠中のヒトとコミュニケーション
夢を見ている最中の人間とコミュニケーションが取れた、との研究結果がある。研究を行ったのは、米ノースウエスタン大学のKen Paller研究室だ。Paller教授は心理学者であり、同大学の認知神経科学プログラムの担当者である。
本研究では、実験前に被験者が睡眠中に自らが応答する方法についてトレーニングを受けた。トレーニングでは、顔を動かす方法や眼球運動の練習が行われた。
睡眠の状況はポリグラフ法で観測がされ、被験者がレム睡眠状態になると研究者が質問。例えば、「8-6」という計算問題が出されると、19歳の被験者は3秒以内に2回、眼球を左右に動かすことで「2」と回答した。被験者はトレーニングを受けているが、質問の内容は事前に知らされていないという。
また、被験者の運動機能面での動きだけでなく、脳波にも動きが見られた。
実験では、36人の被験者に対し合計158回のコミュニケーションが試みられ、そのうち18.4パーセントは正しい回答が出たとしている。
本研究は、夢であるとの自覚がある明晰夢がテーマの一つ。研究室は、睡眠中の意識や認知だけでなく、夢のレポートの正確さを評価する、悪夢への対処法の探求などにも活用できるとしている。
夢技術開発を進める3社|スタートアップは米2社を紹介
今後、検証は必要になるであろうが、以上のように人が見る夢に何らかの影響を与えることが技術的に可能であるようだ。そして、消費者を相手に夢に関するデバイス、ソリューションをつくる企業もすでに存在する。
3社を取り上げる。
 3社のうちスタートアップに該当する2社の概要。公開情報より編集部制作
3社のうちスタートアップに該当する2社の概要。公開情報より編集部制作
Prophetic「Halo」
2023年に米ニューヨークで設立したPropheticは、「Halo」という名のデバイスを開発中だ。ベースとなる考え方は先ほどのノースウエスタン大学に近く、Haloによって明晰夢を誘発しやすくする。
Propheticの説明によると、明晰夢でない夢を見るときは脳の背外側前頭前野(dlPFC)の活動が低下する。そして、明晰夢は反対にdlPFCが活発に動くという。環状のHaloをかぶり、集束超音波ビームを使用して、明晰夢に関与する特定の脳領域を刺激することで、dlPFCの動きを促す他、脳波検査 (EEG) や機能的近赤外線分光法 (fNIRS)での計測も行う。
同社は、明晰夢の誘発を通して、人の生産性向上や創造性の向上へ繋げることを狙っているようである。
2025年春の発売を予定していたが、現状ではまだ出荷されていない模様だ。
REMspace「LucidMe」
米シリコンバレーのレッドウッドシティに本拠を置くREMspaceも、Propheticと同様に明晰夢が見られるよう刺激を与えるデバイスを開発。形状はアイマスクで、「LucidMe」と名付けられたものだ。
LucidMeの紹介動画
LucidMeは、AIモデルを搭載し音・光を出す構造となっている。これらにより、明晰夢を見るためのヒントが脳に与えられる他、いびきの大きい人には寝る姿勢を変えるよう促す、睡眠の状態を計測しながらできるだけ自然なタイミングで起こす、といった機能も備える。また、関連するスマートフォンアプリやサプリメントも開発している。
LucidMeも2025年3〜4月にリリース予定だったが、まだ出荷されていないようだ。
Philipsも夢の記憶を強化する脳刺激技術を特許出願
商品化するかは不明であるものの、ヘルスケア機器大手のPhilipsは2020年、被験者の脳波(EEG)などから睡眠状態、特にレム睡眠をリアルタイムで検出し、そのタイミングに合わせて聴覚・触覚などの感覚刺激を与える特許を出願している。この技術は「夢の記憶を強化するシステム」であり、EEGは「シータ範囲」とのことで、周波数が4〜7.5ヘルツのシータ波を指すと見られる。
さらに、ディープラーニングなどの機械学習モデルを用いて睡眠段階を検出・予測し、刺激制御にフィードバックする点も特徴的である。ウェアラブル機器としての実装も想定されている。
期待されるデジタルヘルスへの応用
冒頭で示した常松氏によるレビューのように、夢に関する研究は全体を俯瞰すればまだ途上であり、解明できていない部分の方が大きいと見るのが自然だろう。すでに何らかの結果が出ている研究も、今後、裏付けを求められるケースが出てくるはずだ。
一方で今回見たように、数は多くないが、夢を解析するような技術や夢を制御するような技術の研究開発の事例も登場している。事例で見たように、より良い睡眠を取るように誘導すること、メンタルヘルスや精神疾患への応用、生産性や創造性の向上などの用途が期待されるが、現状では実用化には多くの時間がかかるだろう。
参考文献:
※1:What are the neural mechanisms and physiological functions of dreams?, 常松友美, Science Direct(リンク)
※2:Dreaming and the brain: Toward a cognitive neuroscience of conscious states, J. Allan Hobson他, Research Gate(リンク)
※3:Neural Decoding of Visual Imagery During Sleep, 神谷之康他, Sciencexpress(リンク)
※4:睡眠中の脳活動パターンから見ている夢の内容の解読に成功, ATR(リンク)
※5:Targeted Dream Incubation, MITメディアラボ(リンク)
※6:Dormio: Interfacing with Dreams, MITメディアラボ(リンク)
※7:Real-time dialogue between experimenters and dreamers during REM sleep, Ken A. Paller他, Current Biology(リンク)
※8:Real-time dialogue with a dreaming person is possible, Stephanie Kulke, Northwestern Now(リンク)
※9:Prophetic(リンク)
※10:REMspace(リンク)
【世界の脳関連デバイスの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】
世界の脳関連デバイスの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。
CONTACT
お問い合わせ・ご相談はこちら